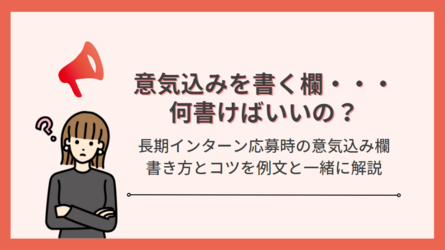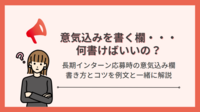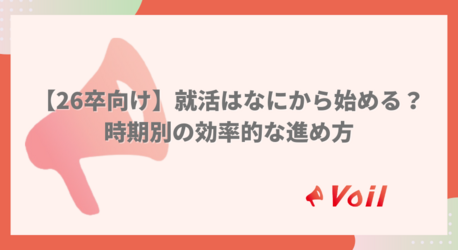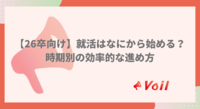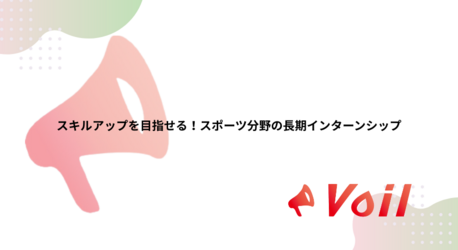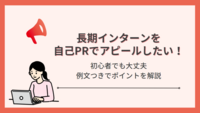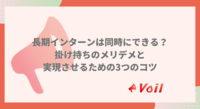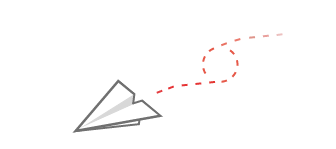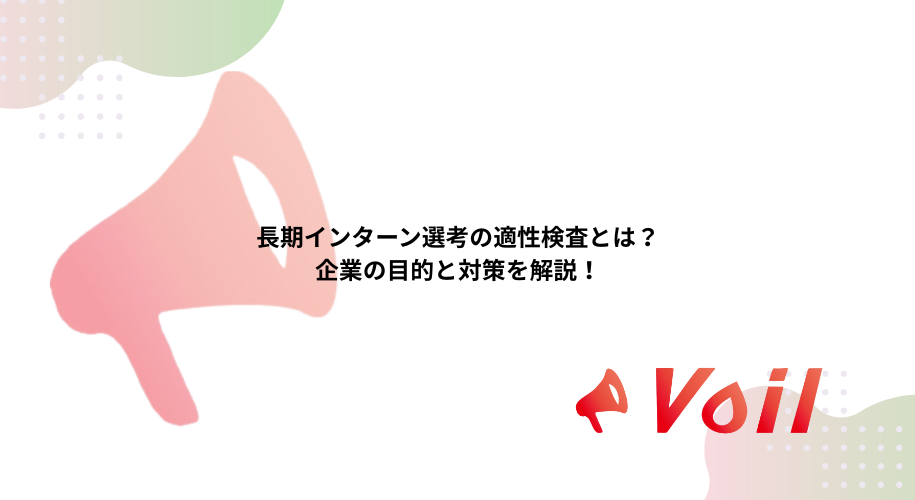
長期インターン選考の適性検査とは?企業の目的と対策を解説!
長期インターンとは
長期インターンとは、学生が企業で働き、実務経験が積めるインターンシップのことを指します。
長期インターンでは、学生でも社員と同様の仕事を任されます。
そして、その仕事が労働とみなされることにより、学生にも給与が支払われます。
長期インターンの給与形態は、主に時給制、日給制、成果報酬制の3つです。
長期インターンの参加期間は3ヶ月以上が一般的であり、専門的なスキルを身に着けるには半年〜1年以上の継続が求められています。
長期インターンを実施している会社はベンチャー企業が多く、また首都圏の求人数が多いため、1ヵ月以上の長期インターンを経験している学生は東京圏に集中している傾向があります。
また、長期インターンの期間が長くなるほど、理系学生の参加割合が高いです。
参考記事:https://mtip.umbc.edu/resources/what/
インターン採用における適性検査とは?
インターン採用における適性検査とは、企業が学生の性格や能力、行動様式などを評価するためのツールのことを指します。
適性検査には、2つの検査があり、能力検査と性格検査に分類されています。
能力検査では、言語や数的、論理的思考力などの基礎的な学力を測っており、性格検査では、学生の個性や価値観、行動の傾向などを測っています。
適性検査には、SPIや玉手箱などという業界標準の検査もあれば、企業が独自に作成したオリジナルの検査もあります。
インターンでの適性検査の目的は?
インターン採用で適性検査を実施する目的は、学生が自社に適している人物であるかを判断するためです。
具体的には、学生がどのような職種や業務に向いているかを見極めています。
特に、性格診断の結果は企業が求める人物像と照らし合わせることに役立っており、ミスマッチを防ぐ役割もあります。
また、応募者が多く応募者全員と面接を組むことが難しい場合は、適性検査を用いることで、自社に合った人材を時間とコストを削減して選定していく手段にもなっています。
適性検査の内容と対策!
インターン採用で適性検査がある場合、どうすれば合格になるのか気になりますよね。
能力検査は学力を測るものなので、勉学が重要になりますが、性格診断は個性や価値観を見ているので必ずしも正解があるわけではありません。
ここでは、インターン採用における適性検査の内容と対策についてお伝えしていきます。
まず、適性検査の内容ですが、用いられるツールによって多少異なる部分があります。
基本的に適性検査で測られる適性は、一般的な学習能力を測る知的能力、言語を理解し使いこなす言語能力、計算を正確に速く行い、応用問題を解いていく数的能力などです。
そのほか、空間判断力や図形の差異を見分ける形態知覚もあります。
また、身体を動かす検査になると、指先や手腕の器用さを測る検査が実施される場合もあります。
能力検査の対策は、問題を時間内に解き切るために、過去問を解いたり、模擬テストを受けたりすることがおすすめです。
出題される問題レベルは中学生~高校生レベルですが、解答時間が限られているため、スピードが求められます。
したがって、本番に近い環境で時間をきちんと計り、テスト形式に慣れることができる模擬テストを受けておきましょう。
また、過去問を解いてみて苦手箇所を理解し、重点的に勉強することも対策の1つです。
性格診断については、正直に回答することがベストです。
ただし、自分のことを理解していないとスピーディーに回答していけないため、ESや面接対策にもなる自己分析をしておきましょう。
自分のことを理解していれば、テキパキと回答できるだけでなく回答の矛盾も防ぐことができます。
適性検査では偽りが見抜かれやすいので、別の回答と矛盾してしまう答えにしていないかが重要なポイントとなっています。
参考記事:https://www.jil.go.jp/institute/seika/tools/GATB.html
参考記事:https://shigoto.mhlw.go.jp/User/GTest/Introduction/Part1
著者の体験
私は大学3年生のときに長期インターンを始めましたが、その際は適性検査の受検はありませんでした。
しかし、短期インターンシップへ申し込む際は適性検査の受検が必須だったので、企業によって導入しているところとそうでないところがあるようです。
とはいえ、就活では複数社の企業の選考を受けていくことになるため、適性検査の対策をしておいて無駄はありません。
大手企業や有名企業など応募者数が多い企業は、全員と面接を実施する時間が足りないため、適性検査を実施して選考通過者を選抜している傾向があります。
過去の口コミを調べるだけでなく、選考を受ける会社の規模感や募集人数と応募者数の関係などから、適性検査の有無を考えてみるといいかもしれません。
また、長期インターン中や就職後は労働者の適性を図るために、社内で適性検査が実施されることがあります。
実際に私もいくつかの会社で仕事をしてきましたが、簡単な適性検査を受検してきました。
適性検査のうち、能力検査は対策がしやすいですし、性格検査も自己分析をしておくと回答しやすくなりますよ。
まとめ
今回は、長期インターン採用における適性検査について解説しました。
適性検査には、能力検査と性格検査があり、用いられるツールによって検査内容が異なります。
SPIや玉手箱など多くの企業が導入しているツールは対策がしやすいので、問題集などを買って反復的に勉強しておくといいですね。
また、性格診断にスラスラ答えていくためにも自己分析をして、自己理解を深めておきましょう。