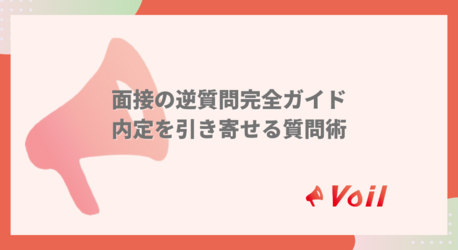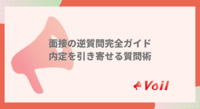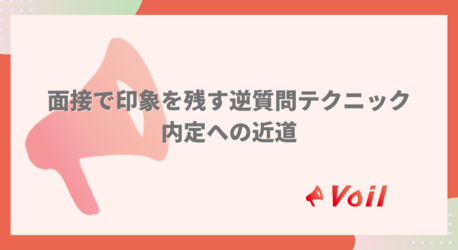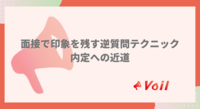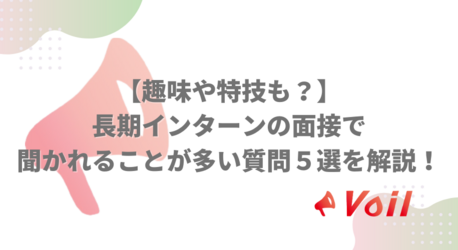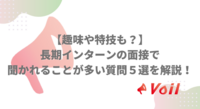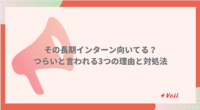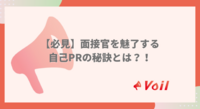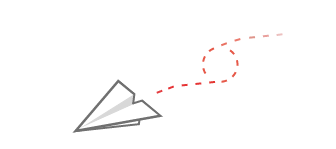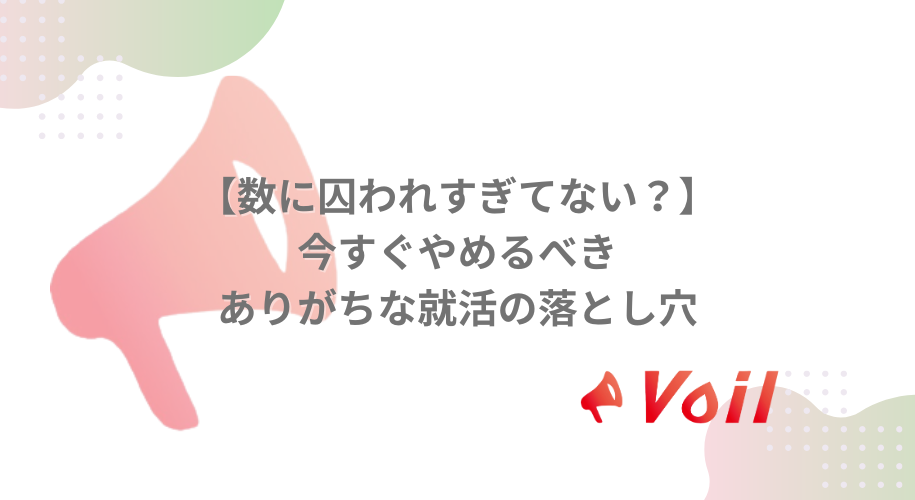
【数に囚われすぎてない?】今すぐやめるべき、ありがちな就活の落とし穴
平均何社受けるの?
周りの就活生がどのくらいエントリーしているか気になりますよね。
株式会社マイナビが2024年卒業予定の全国の大学生、大学院生を対象に、実施した調査では、平均エントリー数は14.7社でした。
この結果は、前年比1.5社減であり、インターンシップ参加者数が多い学生ほど、エントリー数も多い傾向にあります。
社数に「無難」はあっても「正解」はない
平均エントリー数を知って、何社受けるべきか迷っている人が多いでしょう。
結論、平均社数は出されていますが、エントリー数に正解はありません。
そのため、学生一人ひとりによってベストな社数は異なります。
多くの就活生が周りと比べて「少ないかな」「多すぎるかな」と不安になりがちです。
しかし、5~15社が無難とされていても、就活をうまく進めるためには自分にベストな社数を受けることが重要です。
社数を気にしてしまうのはこんなとき
受けるべき社数は人それぞれと言われても、自分にベストな社数を理解するのは簡単ではないですよね。
周りと比べないようにしても、友人の話やSNSと比較してしまうと思います。
自分次第の就活でなぜ社数を気にしてしまうのでしょうか。
そこで、ここでは受験社数を気にしてしまうのはどんなときかを解説します。
①周りと比較してしまう
多くの就活生は、周りと比較したときに自分の受験者数が気になります。
具体的には、友人と就活の話をしたり、SNSで多くの就活生の状況を見たりしたときです。
そして、「みんなそんなも受けているの?」と自分の社数に不安を感じてしまうのです。
自分より多くエントリーしている人を知ると、焦ってしまうこともあるでしょう。
②内定はもらったが少数しか受けていない
内定をもらっていても、少数しか受けていないと周りのエントリー数が気になってしまいます。
内定はもらったものの、多くの企業を見ていないと「本当にここでいいのかな」「まだ他があるんじゃないか」と思えてくるのです。
また、比較検討していないと自分の条件に合っているのかがわからず、承諾に踏み切れないケースも考えられます。
③早いタイミングで就活を終えた
内定をもらい早いタイミングで就活を終えたときも周りのエントリー数が気になることがあります。
周りより一足先に就活を終えた際、まだ続けている就活生の情報を目にすると、「2・3社しか受けていないけどここでいいのかな」と思えてきます。
まだ就活を続けられる時期ではあるので、もう少し見てみようかなと思うのです。
数字を意識して受験企業を増やすのは本質的ではない
いろいろな情報を得ることで、自分のエントリー数は適切かどうか不安になってきます。
しかし、ここで平均くらいは受けておこうと焦って動くのはあまりおすすめできません。
もちろん平均社数を意識するのは大事ですが、一気に受験企業を増やすのは自分のためにはならない場合があるからです。
選考スケジュールが重なり、準備が疎かになったり、軸からズレた企業を受けたりするリスクがあるため、慎重に考えましょう。
こういう時は視野を広げてみよう
周りの就活生が何社受けるのか気になると、うずうずしますよね。
自分のエントリー数が心配になったときはどうしたらいいのでしょうか。
ここでは、視野を広げてみるのが対策になる場合を紹介します。
受けている企業に納得がいっていないとき
まず、受けている企業に納得ができていないときは、社数を気にするのではなく、視野を広げてみましょう。
同じ業界、職種ばかりを受けているときは違う業種に目を向けることが大切です。
また、納得いかない状態が続いているときは、就活の軸をもう一度見直しましょう。
自己分析が足りておらず、自分に合った軸を考えられていない場合がありますよ。
選考になかなか慣れないとき
就活をしているけれど、なかなか選考に慣れてられない人がいると思います。
その場合は、選考数が足りていない可能性が高いです。
そのため、エントリー数を増やし、選考に慣れる機会を作りましょう。
また、視野を広げて他の業界を受けたりして、いろいろな選考の雰囲気を掴んでみてください。
自分の気持ちが言語化できないとき
就活をしているものの、自分の気持ちが言語化できないときは、視野を広げるべきときです。
なぜなら、言語化が難しい場合は、自分に合った企業を受けておらず、モヤモヤしている可能性があるからです。
そんなときは、今まで見ていなかった条件や軸で新しい企業を見てみましょう。
受ける企業の種類が変われば、自分の気持ちにも変化が訪れるかもしれませんよ。
2,3社しか受けていないけど問題ない?
平均エントリー数を知って、自分は少ないと感じた人もいるでしょう。
受けるべき社数は人それぞれなので、少なくても問題ない人はいます。
しかし、不安になると思うので、ここでは2・3社しか受けていなくても問題ないかどうかについて解説していきます。
納得がいけば数社でも問題ない
結論、本人が納得いっているのであれば、数社でも問題はありません。
大事なのは、社数ではなく納得して内定承諾できるかです。
2・3社しか受けていなくても、内定をもらってその中で承諾できるのであれば、納得しているということになります。
そのため、周りのエントリー数は気にすることなく、2・3社で終わって大丈夫です。
違和感を感じているなら、企業数を増やしてみるのも1つ
2・3社しか受けていない状態に、違和感を感じているのであれば、エントリー数を増やしてみましょう。
違和感は行動することでしか解決できません。
むやみやたらに増やすのはおすすめできませんが、軸や条件に沿って少しずつ増やしてみてください。
比較検討できるようになることで、何が違和感だったかにも気づけるでしょう。
まとめ
今回は、ありがちな就活の落とし穴である、エントリー数について解説しました。
いろいろなサイトで平均エントリー社数が出ています。
しかし、それはあくまでも平均であり、就活生全員が適度なエントリーをしているわけではありません。
2・3社しか受けず就職先を決める人もいれば、30~40社受けて比較検討する人もいます。
そのため、周りの状況を気にしすぎずに、自分に適切な数を考えていきましょう。